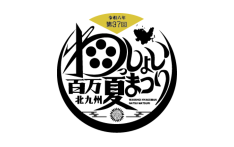夏まつり大集合

北九州市7区が誇る山笠や山車による大共演会。数々の勇壮・華麗な祭りの迫力や熱気を肌で感じてください。今年は、長崎街道の宿場町として今も貴重な史跡や町並みが残る木屋瀬地区から、木屋瀬祇園山笠が参加します!
- 【場所】小文字通り他
- 【時間】18:20~(小倉祇園太鼓)、19:00~20:50(山車運行)
まつり紹介
曽根の神幸祭
曽根の神幸祭保存会
曽根の神幸祭は、小倉南区曽根新田地区の綿都美神社に伝わる神事です。文化14年(1817年)の暴風雨で甚大な被害を受けた曽根新田の鎮守として綿都美神社を造営し、文政2年(1819年)に五穀豊穣・風鎮汐留を祈願する大祭を行った事が始まりとされています。曽根地区・朽網地区から7基の山車が参加し、祭り期間中、山車が提灯山、幟山、人形飾山へと変化します。今年は朽網東の山車が運行します。
大里電照山笠
大里電照山笠振興会
「大里電照山笠」で打ち鳴らす大里太鼓は、奉納太鼓として遠く一千年前、戸上神社鎮座の頃から始まったとされています。明治の中頃、太鼓の名人広光宮司が神殿で奉納する太鼓が人々の好感を呼び、春・秋の大祭が盛んになりましたが、昭和の一時期途切れていました。昭和46年地元の人々の懐旧の情から郷土芸能として復活し、昭和61年から大里太鼓を乗せ、今日のように華やかに電照されるようになりました。戸上神社春期・秋期大祭、門司みなと祭、門司駅前秋祭りなどに出場しています。
国指定重要無形民俗文化財 小倉祇園太鼓
小倉祇園太鼓保存振興会
江戸時代から約400年続く小倉を代表する夏祭り「小倉祇園太鼓」は山車の前後に据えた2台の太鼓の両面打ちとヂャンガラという摺り鉦の音が織りなす「太鼓の祇園」です。勇壮な太鼓の音には天下泰平、国土安泰、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全を願う意味が込められていて、古来より「祇園風に吹かれると夏患いせぬ」と言われています。伝統ある小倉祇園太鼓の魅力に触れてください。今年は東浅野町内会、無法松之碑保存会、金田第一町内会が運行します。
若松五平太ばやし
筑前若松五平太ばやし振興保存会
その昔、肥前の役人「五平太」なる人が燃える石を発見し、以来人々は石炭の事を「五平太」と呼んでいました。石炭は近代日本の産業エネルギーとして活用され、「川ひらた」と呼ばれる小さな船で日本一の石炭積み出し港である若松港へ運ばれていきました。この「川ひらた」の船頭衆達が激しい仕事の合間に船べりを叩きはやしながら、民謡などを口ずさんだのが「五平太ばやし」の始まりです。叩き歩きしながらのかん高い木樽のリズミカルな音色は、見る者の気持ちを浮き立たせてくれます。
2016年 ユネスコ無形文化遺産登録 戸畑衹園大山笠
戸畑衹園大山笠
戸畑衹園大山笠行事の期限は、享和2年(1802年)、筑前国戸畑村に疫病が蔓延し、村人が須賀大伸に平癒祈願を行ったところ終息したため、翌年の享和3年(1803年)7月に解願行事として山笠を作り祝った事からと言われています。2016年、ユネスコ無形文化遺産に登録され、国の重要無形民俗文化財にも指定されている戸畑衹園大山笠の最大の特徴は、昼の古式ゆかしい「幟大山笠」が夜になると飾りをはずし、12段309個の提灯に彩られた光のピラミッド「提灯大山笠」へと姿を一変するところです。
一基あたり約80名、交替を含めると、200~300人の担ぎ手が鉦や太鼓のお囃子に合わせ「ヨイトサ、ヨイトサ」の掛け声で勇壮な光の絵巻を繰り広げます。今年は西大山笠、西小若山笠が運行します。
八幡東ねぶた
八幡東ねぶた振興会
八幡東区で20年前に産声を上げた新しいお祭り、ねぶた祭り!ご存知のように八幡東区は製鉄所の街【火の町】です。鉄を溶かす溶鉱炉の火を連想させるお祭りが【ねぶた祭り】です。歴史の深い北九州市の祭りの中で地域に賑わいを!子どもたちに夢を!を合言葉に生まれた新しいお祭りです。ねぶたは全て会員の手作りで、今年は菅原道真さんの鬼神と、時の権力者藤原時平の武者ねぶたに合わせ、風神雷神ねぶたを組み合わせて登場させます。ねぶたの良いところは、笛・太鼓・はねとが気持ちを一つにして、老若男女問わず誰でもすぐに参加できる事です。